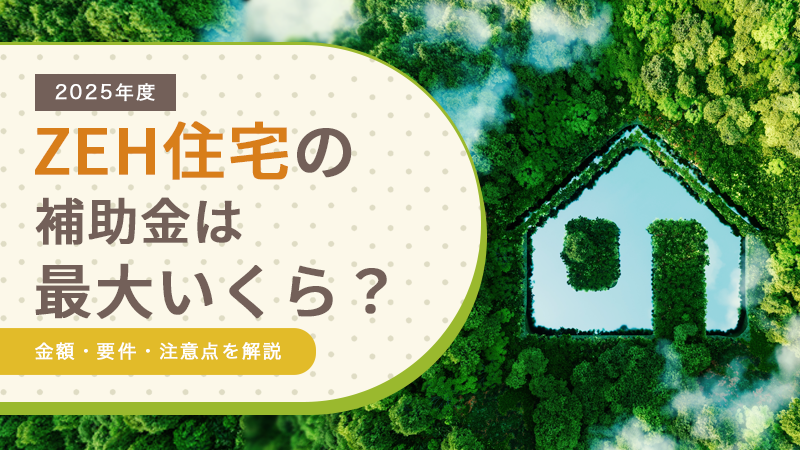ZEHを立てる際は、国の補助金制度や各種優遇措置が活用できることをご存知でしょうか。
ZEHでは、高性能な断熱材やエネルギー効率の高い設備の導入が求められるため、初期費用がかかりやすい傾向にあります。しかし、こうした制度を理解しておくことで、お得に賢くコストダウンを図れるでしょう。
この記事では、ZEHの基本的な紹介から、2025年度の補助金制度の詳細、申請の流れまで、最新情報にもとづいてわかりやすく解説します。
ZEHとは
ZEH(ゼッチ)とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(Net Zero Energy House)」の略称で、年間の一次エネルギー消費量が実質ゼロ以下になる住宅を指します。
これは、住宅の断熱性能を高めることで冷暖房などのエネルギー使用を最小限に抑えつつ、太陽光発電などの再生可能エネルギーによって必要なエネルギーをまかなう仕組みです。
ZEHは地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上を目的に、国が推進する住宅のあり方です。高断熱・高効率設備・創エネの3要素を備えることで、快適な室温を保ちつつ、光熱費の削減にもつながることから、近年注目を集めています。
2023年には住宅の省エネ基準が見直され、断熱性能や設備仕様の全国的な基準が強化されました。
さらに2025年4月以降、新築住宅には省エネ基準の適合が義務化されます。すなわち、すべての新築住宅は、一定の省エネ性能を満たすことが必須条件となるのです。2030年には、ZEH水準そのものが新築住宅の基準となる方針も示されており、今後ZEHの重要性はさらに増すと考えられます。
こちらの記事では、ZEHについてさらに詳しく解説しています。 ZEH認定の要件やメリットについて紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
【2025年度】ZEH補助金の概要と種類
2025年度も、ZEHを対象とした補助金制度が継続されています。正式名称は「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」で、省エネ住宅の普及と再生可能エネルギーの導入を促進する目的で、国が実施している制度です。
「ZEH」「ZEH+」「追加設備導入」の3つの枠組みに分類されており、それぞれに要件と補助金額が異なります。
ここでは、個人でZEH補助金の利用を検討している方向けに、要件や制度の内容を解説しています。法人での申請を検討されている場合は、別途ご確認ください。
出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ「令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業)公募要領 <個人申請編>」(以下公募要領)(https://zehweb.jp/assets/doc/R07ZEH_moe_kouboyouryou_kojin.pdf)
出典:環境省「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業(経済産業省・国土交通省連携事業)」(https://www.env.go.jp/content/000248499.pdf)
ZEH補助金
ここでは、2025年度のZEH補助金制度について紹介します。
主な要件
ZEH補助金の対象となる住宅は、第三者監査であるBELSで「ZEH(交付要件を満たす場合に限り、Nearly ZEH、ZEH Orientedも可)を満たしていること」、かつ一次エネルギー消費量を20%以上削減できることが前提です。
さらに、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備を設置し、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロ=100%削減する必要があります。(Nearly ZEHでは75%削減、ZEH Orientedでは20%削減を必須とする)
金額
ZEHの補助金額は、1戸あたり55万円です。地域の区分や建物の大きさに関係なく、全国一律で支給されます。
公募期間
2025年度における一般公募期間は以下のとおりです。
・単年度事業:2025年4月28日(月)~12月12日(金)
・複数年度事業:2025年11月7日(金)~2026年1月6日(火)
申請は、平日のみ受け付けており、毎日17時が締切です。
公募方法と選択方式
ZEH補助金の公募は【先着順】で受け付けます。提出書類に不備や不足がある場合、申請は受理されません。
なお、申請総額が予算の上限に達した場合、該当日の17時までに届いた申請のうち、書類に不備のないものを対象として抽選が実施されます。抽選結果は、申請受付から1週間以内に通知されます。
申請数や予算の残額は、SII(環境共創イニシアチブ)の「ZEH Web」で随時公開されるため、申請タイミングの目安として活用しましょう。
ZEH+補助金

南向き大開口でもプライバシーを確保した大空間LDKのあるゼロエネ住宅 大阪府/(有)ファーストプランテクノ
ここでは、ZEH+補助金の概要を紹介します。
主な要件
ZEH+は、ZEHよりも高性能な住宅を対象とした補助金です。まず、ZEHの要件を満たしたうえで、断熱等性能等級6以上でなければなりません。さらに、再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費量の30%削減を達成していることも条件となります。
これに加え、以下の要素のうち、ひとつ以上満たす必要があります。
高度エネルギーマネジメント(HEMS)の導入 再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置
より快適で省エネ性の高い暮らしを目指す方は「ZEH+」の採用が適しています。
金額
ZEH+補助金は、1戸あたり90万円です。ZEHの55万円に比べて高額ですが、その分、求められる性能も高くなります。
公募期間
ZEH+の公募期間は、通常のZEH補助金と同様です。
・単年度事業:2025年4月28日(月)~12月12日(金)
・複数年度事業:2025年11月7日(金)~2026年1月6日(火)
選択方式
ZEH+補助金も、先着順で受け付けます。スムーズな申請には、ZEHビルダーと連携しながらの設計と書類準備が必要です。
追加設備等による追加の補助金
ZEHまたはZEH+仕様の住宅に、先進的な設備を追加導入することで、補助金をさらに上乗せして受けられます。対象設備と補助内容を紹介します。
蓄電システム
家庭用蓄電池を設置する場合は、以下のなかからいずれか低い補助金額が加算されます。
1.初期実効容量1kwhあたり2万円
2.蓄電システムの補助対象経費の1/3
3.補助額上限20万円/戸
再生可能エネルギーの自家消費率を高める設備として推奨されており、導入することで電気代の削減や災害時の備えにもつながります。蓄電システムが対象となるには、仕様や性能など詳細な技術要件をクリアしなければなりません。
直交集成板
木造の断熱性や遮熱性などを高める直交集成板(CLT)を構造材に使用することで、一戸あたり90万円の定額補助が受けられます。
ただし、直公集成板は、国内製品かつJAS認定工場で製造されたJAS製品に限られます。仕上げ材の一部や、化粧材・柱の一部として使用した場合は、補助の対象外です。
地中熱ヒートポンプ・システム
地中熱ヒートポンプとは、地面の中に蓄えられた安定した温度の熱(地中熱)を活用して、冷暖房や給湯を行うシステムです。設置した場合には、一戸あたり90万円の定額補助が支給されます。
PVTシステム
PVTシステムは、太陽光発電と太陽熱利用を組み合わせたハイブリッド設備です。補助額は、パネルの面積や形式によって65万円から90万円となります。
ただし、原則として、日本国内で市場流通されている製品が対象です。
太陽熱利用システム
太陽熱を利用して給湯・暖房を行うシステムも補助の対象です。補助金額は、一戸あたり12万円から15万円で、パネル面積によって異なります。
太陽光発電が太陽の光で電力を生み出して幅広く使えるのに対し、太陽熱利用システムは主に急騰や暖房など「熱」の用途に特化しています。
ZEH補助金を利用する際の流れ

ZEH補助金の申請には、専門的な知識と多くの書類が必要です。申請手続きや要件の確認は、主に住宅を建てる建築会社の担当範囲です。
ここでは、ZEH補助金を利用する際の流れを紹介します。
実際の申請はビルダーが行う
ZEH補助金の申請は、基本的にZEHビルダーが代行します。施主が行う作業はほとんどなく、交付申請や実績報告といった手続きも、公募要領を熟知したビルダーが責任を持って対応します。
というのも、ZEH住宅を建てられるのは「ZEHビルダー」に登録された事業者に限られているためです。ZEHビルダーとは、年間の住宅供給におけるZEHの割合など、国の基準を満たしたハウスメーカーや工務店、設計事務所、リフォーム会社、分譲住宅会社などを指します。
これらの事業者は「一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)」が認定・公表しており、国のZEH普及施策と連携して活動しています。まずはSIIが認定した「ZEHビルダー」に相談することが、補助金活用への第一歩です。
ZEH補助金利用の流れ
ZEH補助金を利用する際の流れは、以下のとおりです。
1.ZEHビルダーに相談する
2.プラン(間取り・仕様・予算)を決定する
3.補助金申請する
4.工事に着工する
5.補助金を受け取る
住まいづくりには、予算や間取り、設備など、多くの検討ポイントがあります。ZEH性能を満たすことに加え、長く快適に暮らせる住まいかどうかが何より重要です。
ZEH補助金のスケジュール
ZEH補助金の申請には、いくつかの募集区分があり、それぞれ申請スケジュールが異なります。2025年度は以下の4種類が設けられています。
・一般公募(単年度)
・一般公募(複数年度)
・新規取組公募
・複数年度事業の2年目
たとえば、一般公募(単年度)の受付は2025年4月28日(月)10:00開始、締切は同年12月12日(金)17:00までとなっており、交付決定は12月24日(水)です。
一方で、新規取組公募の締切は2025年8月29日(金)、複数年度事業の2年目は同年5月23日(金)までと、区分によって大きく異なります。
また、BELS取得後の中間報告や、住宅完成後の完了実績報告の提出期限も定められています。とくに、事業完了後15日以内の完了報告はすべての区分で必須です。これを怠ると補助金が受け取れない可能性があるため、注意が必要です。
申請スケジュールや各種報告の期限は、必ず公式の公募要領を確認し、ZEHビルダーや関係者と連携しながら進めましょう。
子育て世帯は子育てグリーン住宅支援事業も検討しよう
ZEH補助金とは別に「子育てグリーン住宅支援事業(旧・子育てエコホーム支援事業)」という制度も用意されています。子育て世帯や若者夫婦世帯に向けた支援策として活用できるため、ZEHとあわせて比較検討しておきましょう。
対象となるケース
GX志向型住宅や長期優良住宅、ZEH水準を満たす住宅など、一定の基準をクリアした住宅が対象です。一般世帯でも申請可能ですが、子育て世帯や若者夫婦世帯であれば、より高額の補助金を受け取れるケースがあります。
補助金の金額
補助金の支給額は、住宅の性能により異なります。
・GX志向型住宅:最大で160万円
・長期優良住宅:子育て世帯の場合、建て替え(古家の除却をともなう場合)で最大100万円。新築は最大80万円
・ZEH水準住宅:建て替え(古家の除却をともなう場合)で最大60万円。新築は40万円
さらに、一定のリフォーム工事をする場合、最大60万円の補助も受けられます。
ZEH化補助金との併用は不可
ZEH補助金と子育てグリーン住宅支援事業は、併用できません。各制度の対象住宅や要件をよく比較し、メリットの大きい補助制度を選ぶことが大切です。
ZEH補助金を利用するときの注意点
ZEH補助金は、上手に活用すれば建築コストを大幅に抑えられる制度です。ただし、手続きを誤ると、補助金が受け取れなくなる可能性があります。
ここでは、トラブルなく補助金を確実に受け取るために、注意しておきたいポイントを紹介します。
早めの申請がおすすめ
ZEH補助金は予算の上限があり、先着順で受付・採択が進みます。建築予定の地域や年度によっては、国の補助金とは別に自治体独自の支援制度が用意されていることもあるため、それぞれの申請期間や条件を事前に確認しておきましょう。
ビルダーによっては手数料がかかる
ZEH補助金の申請は、基本的にビルダーが代行します。ただし、ビルダーによっては、申請代行手数料などを別途請求するケースがあります。
申請には、専門的な設計図の作成や高度なエネルギー計算、多くの書類提出が必要です。そのため、手数料には「技術的なサポート費」としての性質も含まれていると考えられます。
申請前には、手数料の金額や内訳、補助金が不採択となった場合の返金条件など、契約内容をしっかり確認しておきましょう。
申請後の設計変更はできない
補助金は、提出された設計図をもとに省エネ性能などが審査され、内訳に応じて支給額が決定されます。そのため、申請後に設計内容を変更することは原則として認められていません。
補助金を確実に活用するには、申請前に設計プランを十分に検討し、納得のいく内容で提出することが重要です。
定期報告の義務がある
ZEH補助金を受給した場合、居住開始後2年間は定期報告アンケートへの回答が義務づけられています。
これは、補助金制度を通じて高性能住宅の普及とCO2削減を進めると同時に、実際の住み心地やエネルギー仕様実態を国が把握・検証するためです。具体的には、電気やガスの使用量、太陽光発電システムの発電量などのデータに加え、住み心地に関するアンケートにも協力する必要があります。
確定申告が必要になる
補助金は税法上「一時所得」として扱われるため、原則として確定申告が必要になります。
具体的には、補助金を含めた一時所得の合計が年間で20万円を超える場合、所得税の申告義務が発生します。また、住宅ローン控除を受ける際には、補助金分を差し引いた額が控除対象になる点にも注意が必要です。
住宅ローン控除では「住宅取得価格」から、補助金相当額を差し引いて申告する必要があります。補助金を利用した分は自己負担とは見なされず、そのぶん控除対象額が減ることになります。
さらに、住宅ローン減税の適用を受ける最初の年には、忘れずに確定申告をしましょう。が必要です。
まとめ
ZEH補助金は、家づくりにかかるコストを抑えながら、高性能な住宅を手に入れる絶好の機会です。ZEH基準を満たすことで、エネルギー効率の高い快適な住まいが実現します。
これから家づくりを考えている方は、補助金制度を上手に活用し、安心して理想の住まいを手に入れましょう。
全国の「FPの家」ビルダーは、地域ごとの気候風土を理解した確かな設計力で、ライフスタイルにぴったりの住まいをご提案します。長く快適な住まいづくりをご検討中の方は、ぜひご相談ください。