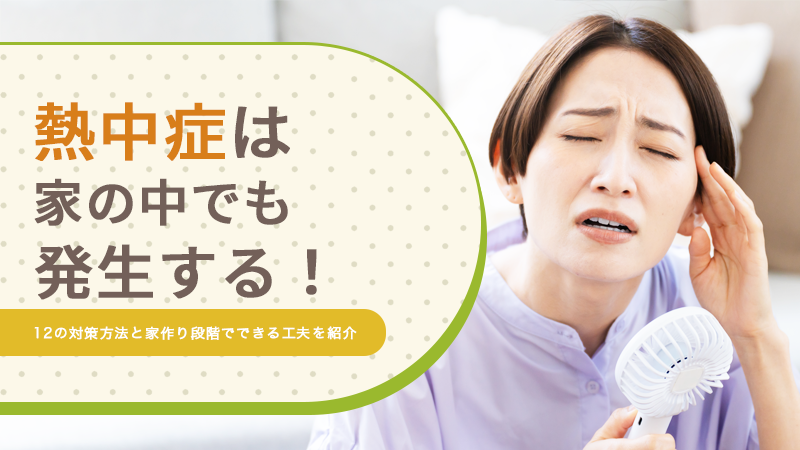夏の暑さが厳しくなるなか「家の中にいれば安全」と考えていませんか?実は熱中症の約40%は住居で発生しており、室内でも十分な注意が必要です。とくに、小さな子どもや高齢のご家族がいる家庭では、日常的な対策が重要になります。
本記事では、室内熱中症の原因から具体的な予防策、さらに家作りの段階からできる根本的な対策まで解説します。熱中症にならないためにも、ぜひ最後までお読みください。
油断大敵!家の中でも熱中症リスクはある
閉め切った部屋や湿度の高い環境では、気づかないうちに体温が上昇し危険な状態になります。まずは、室内熱中症の実態を説明します。
室内熱中症の発生状況
総務省の調査によると、熱中症で救急搬送された人のうち、約40%が「住居内」で発生しています。これは「道路」や「公衆の場」よりも高い割合で、自宅での熱中症リスクがいかに高いかを示しています。さらに、年齢区分別では65歳以上の高齢者が全体の60%を占めており、高齢者が自宅で熱中症を発症しやすい傾向が明らかです。
こうした背景には、室内特有のリスク要因があります。屋外と違い、室内では直射日光を浴びないため体調の変化に気づきにくくなります。「まだ大丈夫」と油断しているうちに体温調節機能が低下し、重症化するケースも少なくありません。
とくに、注意が必要なのは、在宅ワークや家事に集中している時間帯です。水分補給を忘れたり、長時間同じ姿勢で過ごしたりすることで体に熱がこもり、知らないうちに熱中症リスクが高まります。
また、節電の意識からエアコンの使用を控えることも、室内での熱中症の原因になっています。室内にいるからといって油断せず、適切な対策をとることが重要です。
出典:総務省|令和7年6月熱中症による救急搬送状況 (https://www.soumu.go.jp/main_content/001021193.pdf)
室内熱中症になる原因
室内で熱中症が発生する原因は複合的で、環境要因、身体的要因、行動・状況要因の3つの側面から理解する必要があります。ここでは、それぞれをくわしく解説します。
環境
室内で熱中症を引き起こす主な原因は、高温や高湿度、そして風通しの悪さです。これらの条件がそろうと、たとえ屋外ではなく室内にいても、体温調節機能がうまく働かず、熱中症を発症するリスクが高まります。とくに、室温が28℃を超え、湿度が70%以上になると、熱中症の危険性は急激に上昇します。
また、住宅や建物の構造によっても室内の温度環境は大きく左右されます。たとえば、日当たりの良い部屋では、日中に太陽光が直接差し込むため、室温が上がりやすくなります。西向きの部屋は午後から夕方にかけて強い日差しを受けるため、他の方角の部屋よりも高温になりやすい傾向があります。
身体の状態
熱中症のリスクは、年齢や体調によって大きく左右されます。たとえば、高齢者は体温を調節する機能が低下しており、汗をかきにくく、暑さにも気づきにくい傾向があります。
一方、乳幼児は体温調節機能が未発達で、体重に比べて体表面積が大きいため、周囲の気温の影響を強く受けやすくなります。
さらに、糖尿病や心疾患といった基礎疾患を持つ方や、発熱や下痢によって脱水状態にある人も注意が必要です。睡眠不足や疲労の蓄積によって体力が低下しているときも、熱中症のリスクは高まります。
行動・状況
どのような生活を送っているかによっても、熱中症のリスクは大きく変わってきます。たとえば「トイレが近くなるから」といった理由で水分補給を控える行動や、水分補給そのものを忘れてしまうことも危険です。とくに、高齢者の方に多く見られるこのような行動は、脱水症状を引き起こす要因となり、結果として熱中症の発症リスクを高めます。
また、忙しさや集中している作業の中で、水分を取ること自体をうっかり忘れてしまうというケースも少なくありません。さらに、節電意識からエアコンの使用を避けたり設定温度を高くしすぎたりすることで、室内の暑さが我慢できないレベルに達するケースもあります。
家の中で熱中症になりやすい場所

安全に思える家の中にも熱中症のリスクが潜んでいます。油断しやすい場所だからこそ、注意が必要です。ここでは、室内でとくに気をつけたい場所やその特徴について解説します。自宅での熱中症対策を考えるうえで、ぜひ参考にしてください。
キッチン
キッチンは、家の中でもとくに熱中症のリスクが高い場所です。コンロやオーブン、炊飯器などの調理器具が発する熱によって、室温が一気に上昇しやすくなるためです。
とくに、夏場の昼食準備などで複数の熱源を使用すると、キッチンの温度が他の部屋よりさらに室温が上がります。換気扇を使用していても外気温が高いと十分な冷却が得られず、熱がこもりやすくなる点にも注意が必要です。
浴室
浴室とその周辺は高温多湿な環境になりやすく、家の中でも熱中症が起こりやすい場所のひとつです。入浴中はお湯の熱と湯気によって、浴室内の温度と湿度が急上昇します。追い焚き機能を使う場合、長時間にわたり浴槽が温かく保たれるため、浴室全体の温度も高止まりしやすいです。
寝室

寝室では就寝中に熱中症が起こるケースが多くみられます。睡眠中は意識が低下しているため、暑さや喉の渇きに気づきにくく、脱水が進行しやすくなるからです。2階以上の寝室では熱が上昇する性質により、1階と比べて1〜3℃高くなることもあります。
また、エアコンをタイマー設定している場合、深夜に冷房が切れてしまい、明け方の気温上昇とともに室温が急激に高くなるリスクも無視できません。
仕事部屋
在宅ワークの広がりとともに、仕事部屋での熱中症リスクも増加しています。長時間座ったままで作業を続けていると血流が滞り、体温調節がうまくできなくなりやすくなります。また、仕事に集中するあまり暑さや喉の渇きに気づかず、水分補給が疎かになりやすく熱中症のリスクが高まります。
さらに、パソコンやモニター、プリンターなどのOA機器は稼働中に熱を発し、室温の上昇に拍車をかけます。複数台のモニターや高性能パソコンを使用している場合は、より注意が必要です。
ロフト
ロフトは家の中でもとくに熱中症のリスクが高い場所のひとつです。なぜなら、熱は上にたまりやすくロフトは天井に近いため、屋根からの輻射熱を直接受けやすくなり、室温が大きく上がってしまうからです。
さらに、天井が低くエアコンの設置が難しいケースも多く、十分な冷房対策が取りにくいという問題もあります。収納スペースとして使われることも多いため、荷物が多いと空気の流れが悪くなり、より熱がこもりやすくなります。
ベランダ
ベランダでの熱中症は、洗濯物干しや植物の手入れといった短時間の作業中でも起こり得ます。
直射日光と床面の照り返しにより、実際の気温以上に体感温度が上がりやすく、とくに夏場の日中は注意が必要です。南向きや西向きのベランダでは午後の日差しが強く、気温が急上昇しやすいため、より一層の対策が求められます。
室内熱中症を防ぐ!5つの対策方法を紹介
室内での熱中症は、屋外と違って見過ごされやすいですが、そのリスクは決して低くありません。ちょっとした工夫と習慣を続けることで、室内熱中症をしっかり予防できます。
ここからは、効果的な5つの対策方法を解説します。家族全員が安全に快適に過ごせるように、ぜひ実践しましょう。
1:水分・塩分をこまめに補給する
熱中症対策でもっとも基本となるのは、水分と塩分の適切な補給です。「のどが渇いた」と感じたときには、すでに体内では水分不足が進行していることも多いため、のどの渇きを感じる前からこまめに飲む習慣をつけましょう。
とくに、室内にいると汗をかいている実感が少なくなりやすいですが、体内からは少しずつ水分や塩分が失われています。
また、水分補給には水や麦茶などがおすすめです。汗をたくさんかいた日や暑い時間帯には、塩分やミネラルを含んだスポーツドリンクや経口補水液を取り入れるとよいでしょう。 目安としては、1日に1.2リットル程度を分けて飲むとされており、一度に大量に摂取するのではなくこまめに飲むことが大切です。
また、医師から水分や塩分の制限を指示されている方は、自己判断せず必ず医師の指示に従いましょう。大量の汗をかいたときには、塩飴やタブレットなどの補助食品を取り入れるのも有効です。「室内だから安心」と油断せず、こまめな水分・塩分補給を生活習慣のひとつとして意識することが重要です。
2:体調管理を徹底する
熱中症を予防するには、その日の体調に合わせて行動を調整することが非常に重要です。日ごろからバランスのとれた食事と十分な睡眠で、体調を整えておくことが予防につながります。
また、自分自身の体調だけでなく、家族や身近な人との相互チェックも欠かせません。高齢者や子どもは暑さに対する感覚が鈍かったり、自分の不調をうまく伝えられなかったりするため「なんとなく元気がない」「食欲がない」「汗をかいていないのに顔が赤い」といった小さな変化も見逃さないようにしましょう。
3:家の中でもこまめに休憩を取る
室内でも作業や家事に集中しすぎると、体調の変化に気づくのが遅れる場合があります。掃除や料理、パソコン作業などに没頭していると、水分補給や体調の確認をうっかり忘れてしまいやすいです。「室内だから安心」と油断せず、意識的に休憩を挟むことが熱中症対策には欠かせません。
作業場所によっては、環境の影響で体が熱をため込みやすくなるケースもあります。たとえば、空気がこもりやすい場所や冷房が効きにくい空間では、知らないうちに体への負担が増しているかもしれません。
そのため、意識してこまめに休憩を取る習慣をつけることが重要です。休憩時間には軽くストレッチをしたり冷たい飲み物で水分補給をしたりして、体をリフレッシュすると効果的です。
忘れやすい場合は、スマートフォンのタイマーやアラームで休憩のタイミングを知らせる工夫もおすすめです。
4:室内を涼しく保つ
室内熱中症を防ぐためには、室内を涼しく保つ工夫が欠かせません。とくに、高温多湿な日本の夏では、外からの熱の侵入を防ぎ、効率的に冷房を活用することが重要です。
たとえば、断熱性の高い住宅は外気温の影響を受けにくく、室温の急激な上昇を抑えられます。さらに、断熱材がしっかりと施された壁や天井、そして断熱窓を採用することで、日射熱の侵入を大幅に軽減できます。
また、エアコンを使用する際には、冷気が逃げにくいよう環境を整えることがポイントです。カーテンやブラインドで直射日光を遮り、冷気を効率よく保つ工夫をしましょう。
省エネ型のエアコンを適切に使えば、快適な温度を維持しながら電力消費も抑えられます。住まいの構造と家電の特性をうまく組み合わせることで、熱中症のリスクを減らしながら、安心・安全な室内環境を実現できます。
5:風通しをよくする
風通しをよくして「熱」と「湿度」を効率よく逃がすことが重要です。空気がこもったままだと、室温だけでなく湿度も上昇し、体内の熱が放出されにくくなり、熱中症のリスクが高まります。
十分な開口部が設けられていると、自然な風の通り道を確保しやすくなり、こもった熱や湿気をスムーズに外へ排出することが可能になります。
開けられる窓が対角線上に2か所以上あると、空気の流れが生まれ、より効果的な換気が行えます。住宅を建てる際やリフォーム時には、設計段階から通気性を重視することが大切です。
通風を意識した間取りの工夫、高い位置に設ける高窓や、空気の通りを促す通風孔の導入は、室内環境の快適さを保つうえで大きな効果を発揮します。
また、近年では通風性に優れた建材や設備も数多く登場しており、たとえば通気性を高めるサッシや、虫の侵入を防ぎながら風を通す高機能な網戸などがあります。これらの住宅面での工夫を積極的に取り入れることで、エアコンに過度に依存せずに、自然の風をうまく活かしながら熱と湿気をコントロールできます。
空間・素材・質感を大切にした、五感に響く家の事例はこちらから!
家の場所ごとでできる室内熱中症対策の方法
家の中では場所によって熱がこもりやすかったり、換気がしにくかったりすることがあり、それぞれ異なる対策が必要です。
ここでは、部屋ごとに効果的な熱中症対策を紹介します。室内熱中症のリスクを減らすためにも、ぜひチェックしましょう。
リビング
リビングでは家族が集まるため、どうしても熱気がこもりやすくなります。そのため、エアコンは28度以下に設定し、扇風機やサーキュレーターを使って冷気を部屋全体に循環させましょう。
たとえば、テレビやパソコンなど電化製品を使いすぎるとさらに室温が上がるため、不要な時は電源を切るよう心がけます。定期的に窓を開けて換気し、新鮮な空気を入れることも重要です。
日中はカーテンやブラインド、遮熱フィルムを利用して強い日差しが室内に入らないようにすると、室温の上昇を抑えられます。
キッチン
キッチンでは調理中に火を使うことで室温が急上昇します。必ず換気扇を回し、窓とドアを開けて熱を外に逃がす工夫が必要です。電子レンジや電気調理器などを活用すると、発熱を最小限に抑えられます。
たとえば、暑い時間帯は調理を避け、朝や夜の涼しい時間に下ごしらえを終えておくと負担が軽くなります。調理の合間や後にはこまめに水分補給をし、体調が悪いと感じたらすぐに休憩をはさみましょう。
寝室
寝室では、寝ている間に体温調整が難しくなることが多いため、就寝時もエアコンや除湿器を活用し、室温が高くならないよう管理しましょう。エアコンのタイマーやおやすみモードをうまく使うと快適な睡眠環境を保てます。
また、扇風機は直接体に風が当たりすぎないように調節し、寝具は通気性の良いものや冷感素材を選ぶと快適です。寝る前には水分を摂り、夜間の脱水症状を回避しましょう。
子どもや高齢者の部屋
子どもや高齢者は暑さを自覚しにくいため、熱中症のリスクがとくに高くなります。そのため、エアコンや扇風機が適切に動いているか、こまめに確認することが大切です。
また、窓から差し込む強い日差しは遮光カーテンでしっかり防ぎ、室内の温度上昇を抑えましょう。さらに、温湿度計を使って数値で室内環境を管理すれば、熱中症の危険度を把握しやすくなります。
エアコンが設置できない部屋(浴室・脱衣所・トイレなど)
浴室や脱衣所、トイレなどエアコンが設置できない場所では、暑さや湿度の上昇に注意しなければなりません。窓がある場合は必ず開けて換気を行い、扇風機やミニ送風機を使って空気がこもらないよう工夫しましょう。
また、お風呂上がりは体温が高くなっているため、脱衣所で冷感タオルや保冷剤を使って体を冷やすと効果的です。衣類は通気性の良い素材を選び、汗が蒸発しやすいコンディションを作りましょう。
ベランダ・バルコニー・テラス

ベランダやバルコニー、テラスでは直射日光を浴びやすく熱中症のリスクが高くなります。そのため、洗濯物を干すときや作業をする場合は、帽子などで日差しを遮るように心がけましょう。
また、すだれやグリーンカーテンを使うことで建物自体の温度上昇を防げます。作業はできるだけ涼しい朝や夕方に行い、途中で必ず水分補給をすることが大切です。少しでも体調に異変が出た場合は、すぐに屋内に戻り涼しい部屋で休むようにしましょう。
熱中症にかかった際の主な症状と対処法
熱中症は放置すると命に関わる危険もあります。初期症状を見逃さず、早めに適切な対処を行って重症化を防がなければなりません。ここでは、熱中症にかかったときに現れやすい主な症状と、その場でできる対処法を解説します。
命を守るためにも、しっかりおさえておきましょう。
重症度Ⅰ度(軽度)
もっとも軽い段階である重症度Ⅰ度では、次のような症状がみられます。
・めまい ・立ちくらみ ・大量の汗をかく ・こむら返り(筋肉の硬直) など
これらは「熱失神」または「熱けいれん」と呼ばれ、意識ははっきりとしていて、体温の上昇も軽度であることが特徴です。ただし、この段階で油断すると、症状が進行して重症化してしまうおそれがあるため、慎重な対応が求められます。
重症度Ⅰ度(軽度)のときの対処法
症状が現れたら、まずは風通しが良く涼しい場所へ移動させ、衣服をゆるめて安静にします。そのうえで、時間をかけて経口補水液やスポーツドリンクなどを摂取させます。
また、首筋や脇の下に冷たいタオルを当てることで、効率的に体温を下げられます。これらの処置を30分ほど行っても改善が見られない場合は、迷わず医療機関に相談しましょう。
重症度Ⅱ度(中度)
重症度Ⅱ度では、次のような症状が現れます。
・頭痛 ・吐き気 ・嘔吐 ・倦怠感 ・集中力や判断力の低下 など
「熱疲労」とも呼ばれるこの段階では、脱水が進行し、放置すると「熱射病」にいたる可能性があります。この段階での適切な対応が、重症化を防ぐ重要なポイントとなります。
重症度Ⅱ度(中度)のときの対処法
ただちに医療機関への受診が必要な段階です。救急搬送までの間は、風通しがよく涼しい場所で安静にし、体を冷やし続けることが大切です。意識がはっきりしていて吐き気がなければ、水分補給を経口で続けられます。
しかし、嘔吐や意識の変化がある場合は、無理に飲ませないよう注意が必要です体温を下げるには、首筋、脇の下、足の付け根など太い血管がある部分を中心に、氷のうや保冷剤で冷やすと効果的です。
重症度Ⅲ度(重度)
重症度Ⅲ度は生命に危険が及ぶ段階で、次のような重篤な症状が現れます。
・意識障害 ・けいれん ・高体温(40℃以上) など
「熱射病」とも呼ばれるこれらの状態では、発汗が止まって肌が乾燥します。さらに、意識障害やけいれん、言動の異常など中枢神経の障害を引き起こす可能性もあります。このようなときは、体温調節機能が完全に失われているため、早急な専門治療が必要です。
重症度Ⅲ度(重度)のときの対処法
すぐに119番通報し救急車の到着を待ちながら冷却を続けましょう。その際には、氷水や冷水で首、脇の下、足の付け根などを重点的に、できるだけ早く体温を下げることが重要です。
意識障害がある場合は、安全のため、経口での水分補給は行いません。救急隊が来るまで、常に容体を確認しながら処置を続けます。
出典:公益財団法人全日本病院協会|熱中症について (https://www.ajha.or.jp/guide/23.html#:~:text=%E6%9C%8827%E6%97%A5-,%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F,-%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E3%81%A8)
出典:ファストドクター|熱中症の重症度レベルと症状|対応方法・暑さ指数の活用方法まで解説 (https://fastdoctor.jp/columns/heat-stroke-level)
出典:経口補水液OS-1|素早く見つけて、すぐ対策! 脱水症&熱中症 > 熱中症 I 度の症状が見られたら (https://www.os-1.jp/dehydration_heatstroke/dehydration_heatstroke07/)
室内熱中症の対策は家作りの段階から!計画・設計時のポイント
室内熱中症のリスクを減らすには、住まいの環境を整えることが欠かせません。ここでは、設計・建築時に意識したい「熱中症リスクを下げる家作りの具体的なポイント」を紹介します。安全な住まいを目指して、ぜひ参考にしてください。
断熱性に優れた建材を選ぶ
断熱性能の高い建材・仕様の導入は、夏場の室温上昇を抑え、快適な室内環境を継続するうえで最も重要なポイントです。そのため、以下の3つをおさえておきましょう。
窓の断熱対策
窓は家の中で最も熱が出入りしやすい開口部です。そのため、高断熱サッシや複層ガラスの採用、遮熱・断熱フィルムの貼付、外付けブラインド・シャッター・庇の設置などで窓からの熱の侵入を徹底的に防ぎましょう。方角ごとに最適な窓仕様を検討するのが有効です。
屋根の断熱対策
日中、直射日光を最も受けやすい屋根には、しっかりとした断熱材施工が不可欠です。屋根断熱を強化することにより、2階やロフトの熱ごもりを防ぎ、家全体の環境を安定させる効果が期待できます。
壁の断熱対策
外壁にも高性能な断熱材や通気層の導入を積極的に検討しましょう。壁内の通気が確保されることで、季節ごとの熱気の排出や冷気の保持がしやすくなり、各部屋の温度ムラも減ります。
これから家を建てる方にぜひ注目してほしいのが、FPウレタン断熱パネルを用いた「FP工法」です。FPウレタン断熱パネルは、業界最高水準の熱伝導率(0.019 W/m·K)と、断熱力(熱抵抗)約5.5 ㎡·K/Wを誇り、外気の熱を中へ伝えにくくします。
夏場や冬場の室内の急激な温度変化を抑えられる、まるで「魔法瓶のような家」。FP工法の家は、冷暖房の設定温度を抑えることにもつながります。
「FPウレタン断熱パネル」の優れた断熱性のヒミツはこちらから!
通気性のよい設計にする
風通しのよい間取りや開口部の配置は、熱のこもりを防ぎ、自然の力で快適さを保つ重要なポイントです。対角線上の窓を設けて風の通り道をつくったり床下の換気口を設置したりするなど、壁内・天井裏の熱気を効率よく排出できる構造を目指しましょう。
日射遮蔽を取り入れる
直射日光の室内流入を減らすことも、設計段階で意識したい基本対策のひとつです。たとえば、庇やバルコニーを窓に設置すれば、真夏の高い日差しを遮ることができます。
ほかにも、外付けブラインドやシャッター、植栽で「緑のカーテン」をつくるのも効果的です。「日当たり」は住宅選びの重要要素ですが、遮蔽物を適切に設計することで採光と遮熱の両立が実現できます。
まとめ
室内での熱中症を防ぐためには、日ごろのこまめな対策に加えて「家そのものの性能」を高めることが重要です。住宅の設計段階から、断熱・遮熱・通風・日射遮蔽といった要素をしっかり取り入れることで、夏場の室温上昇を抑えやすくなり、快適性や省エネ性に加えて、熱中症などの健康リスクも大きく軽減できます。
「FPの家」では、業界トップクラスの高性能住宅で、長く続く快適な住み心地をご提供します。独自に開発した「FPウレタン断熱パネル」では、最高レベルの「断熱性能等級7」に対応し、優れた気密性と換気システムで室内環境を整えます。
また、地域ならではの気候風土を熟知した地元工務店が家づくりを行うからこそ、お客様一人ひとりの要望にあわせた丁寧な対応が可能です。資料請求も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
こちらから、資料請求を承っております。 「FPの家」の家づくりに関するお問い合わせも可能ですので、 ぜひお気軽にご相談ください。